
CLINKS株式会社はITエンジニアの派遣やアプリ、システムの開発を行ない、在宅勤務に役立つ自社開発ツールも提供しています。
健康経営にも取り組んでおり、「健康経営優良法人2021」の認定を受けた際は、中小規模法人部門で上位企業に与えられるブライト500にも選ばれました。従業員に健康への意識を持たせるためのセミナー実施や人間ドックの費用補助、相談窓口を設置するほか、IT関連企業らしくオンラインツールを活用し、在宅勤務でも社員間のコミュニケーションが取りやすい環境作りにも注力されています。
今回は同社の総務部 部長小林さん、広報部の疋田さん、中田さんにお話をお伺いしました。
完全在宅のエンジニア派遣に注力し、社内の在宅勤務制度も推進

ーーまずは御社について、沿革や事業内容について教えてください。
小林:弊社は2002年に創業し、今年20年目となる企業です。創業当初よりエンジニアの紹介・派遣やシステム開発を主力事業としております。また、最近では居住地を問わずに参画できる、完全在宅のエンジニア派遣にも注力しています。社員数は約930名で、男女比は3対1。平均年齢は30歳ちょっとと、比較的若い社員が多い企業です。
ーー健康経営を始められたきっかけや、健康経営優良法人認定の申請に至った経緯を教えてください。
小林:健康経営に取り組み始めたのは2019年度からで、約3年前からになります。始めた経緯としては大きく2つ理由があり、1つは在宅勤務制度の推進により、メンタルヘルスへの影響が懸念されたことです。以前は、ある程度会社に集まって仕事をするのが当然でしたが、勤務形態が在宅になってしまうと近くに相談する相手がいません。気軽にコミュニケーションが取れず、悩みを抱え込んでしまうとメンタルに悪影響をおよぼすと考えられます。もう1つは、若い社員が多いものの、健康診断の結果を見ると生活習慣病に関する項目で引っかかってくる社員が一定数いたことです。この2点を解決させるために動き出したのが、取り組みのきっかけになります。
当初は加盟している健康組合の認定資格を目指し、2020年に取得できました。そして、2020年の実績をもって、健康経営優良法人の中小規模法人部門にもエントリーした頃、2021年3月にブライト500の認証をいただきました。さらに、健康経営優良法人の大規模法人部門にも挑戦しようということになり、2022年3月に認定をいただけました。2022年はホワイト500には届きませんでしたが、3年前から取り組み始め、少しずつブラッシュアップしております。
ーー在宅勤務制度を整えるようになったきっかけは、何かあったのでしょうか?
小林:弊社は在宅エンジニアの採用とお客様向けの在宅エンジニア派遣サービスも展開しているのですが、このサービスを本格的に稼働させるにあたり、業務の進め方はどのような流れになるのか、どのような困りごとが発生するのか、といった部分でのノウハウを持っておく必要があると感じました。それで、まずは社内で在宅勤務制度を導入し、検証することになりました。
また、弊社代表の理念として、通勤にかかる時間や労力の負担を減らす方向で推進したいという思いがあり、社内での在宅勤務制度を整えていくことになりました。
ーー従業員の皆さまの健康状態について、改善が必要だと感じていた点はありますか?
小林:先ほども申し上げましたが、若い社員が多いものの、健康診断では生活習慣病リスクがあると引っかかる社員が一定数いるのは問題と感じています。あと、メンタルヘルスの部分では、在宅勤務制度が始まってからの課題として挙がっている点です。
ベテランの社員であれば在宅勤務であっても、ある程度、自分のペースをつかんで仕事を進められます。しかし、若手社員の場合、それが難しい部分があります。会社に出勤していれば、すぐ隣の席の社員に相談したりアドバイスをもらえたりする存在がいますが、在宅勤務では物理的に1人の状態です。気軽に相談できる環境でなくなり、困ったときの対処がわからず孤立してしまう社員が一定数いましたので、コミュニケーションが取れる環境作りに課題を感じました。
健康経営の施策にはオンラインツールも積極活用

ーー実際に取り組まれている施策について、詳しく教えてください
小林:年に2、3回のペースで、栄養士さんや産業医の先生などに協力いただいて、食生活や睡眠などをテーマにした1時間程度のオンラインセミナーを実施しました。
食生活のセミナーでは、炭水化物やタンパク質などの摂取バランス、身近にある食品のことや外食も含めて、普段の食生活で最低限これだけは意識してほしいという指導をいただきました。2021年度は、弊社の産業医の先生が精神科医者でしたので、睡眠の質を上げるセミナーにご登壇いただき、睡眠の質を上げるためにできる簡単なことからお話いただきました。
また、健康診断では35歳以上を対象に、人間ドックなどの費用補助も始めています。
それから、社内でのコミュニケーションを活性化させるため、2020年7月からオンラインコミュニケーション手当も始めています。これはオンライン上で社員同士が交流する場合、申請すれば1人1,000円の費用補助を出すというもので、コミュニケーション不足を補って、メンタルヘルスの課題解決になればと始めました。毎月の申請人数は150から200名ぐらいで推移しており、全社員の4分の1弱が利用している状況です。
コミュニケーションの部分で言いますと、社員間の交流機会を増やせるよう、オンラインイベントも行ないました。2020年が一番活発で、2カ月に1度くらいのペースで開催しています。
疋田:オンラインイベントでは、10人前後のチームにわかれて人狼ゲームをやったり、オフラインで交流できた頃からやっていた七夕イベントをオンラインでやったりしましたね。七夕イベントでは、願いごとを書くとそのなかから社長が彦星となって願いを叶えてくれます。
中田:ゲーミングチェアやNintendoSwitchLiteなどが、当たった方がいましたね。
疋田:そうそう、短冊に願いごとを書いて出すと、そのなかから選ばれたお願いを彦星になった社長がプレゼントしてくれます。夏は七夕でしたが、秋はハロウィンイベントを行なって、四季折々の行事をオンラインで楽しんでいます。
小林:弊社はシステム開発も行なっていますので、在宅勤務時も会社内で働いていたときと同じような環境を作り出して、社員同士のコミュニケーションが取りやすくなるツール「ZaiTark(ザイターク)」も開発しました。これは業務中、画面上に自分のチームメンバーの状態が表示され、話しかけて良い状態なのか、作業中や会議中なのかといったステータスも表示でき、ボタン一つでオンライン通話ができるようになっています。このシステムは社内での利用だけでなく、外販してお客様にも提供しています。
公認コミュニティや相談窓口も設置
ーー御社は運動系の公認コミュニティ活動も活発とのことですが、これはコミュニケーションを活発化させる狙いですか?
小林:そうですね、コミュニティ活動は、コロナ禍や在宅勤務が増える以前から、社内の文化として行なわれてきました。コミュニティは申請を出してもらい、承認されれば活動費用の約半額を会社が補助しています。体を動かすスポーツ関連のものが多くなっていますが、ミニ四駆や音楽バンドのコミュニティもあり、部員数はだいたい10から20名ほど。多いところだと30名ぐらい参加している所もあるようです。
疋田:先日も加盟している健康組合のITS野球大会がありました。ITSの大会は、弊社の野球部とテニス部が参加していまして、毎年300社ぐらいのチームが企業対抗の試合をしています。バスケットやバドミントンは中央区の大会に出たり、軽音部はライブ開催に向けてスタジオを借りて練習したり、各部ごとに目標を決めて活動していますね。
小林:以前は新入社員の歓迎会名目で年に2回ぐらい、大きめの会場を借りて開催していた頃があり、軽音部に演奏してもらっていたことがありました。部活ごとに発表の場所や目標、レベルはバラバラですが、それぞれが楽しめるところで参加して、無理のない範囲で交流の場として活用してもらっています。
ーーコミュニケーション強化以外の施策として、各種相談窓口を設けていらっしゃるそうですが、どのようなものですか。
小林:弊社は従業員用の相談窓口を、2種類設けています。1つは完全匿名で利用でき、会社組織の縦割り内では相談しづらい内容も気軽に話せる窓口となっています。基本的にはWeb上でテキストをやり取りしての相談ですが、それだけでは解決しない場合は本人の意向を確認し、ビデオ通話でも相談に乗ってもらえます。
もう1つは、臨床心理士さんや看護師さん、栄養士さんなど、外部の専門職の方にも協力いただいている、健康関係の相談ができる窓口です。こちらは電話相談とテキストでの相談、場合によってはオンライン面談も可能になっています。
評価フィードバックを受けて今後はホワイト500を目指したい
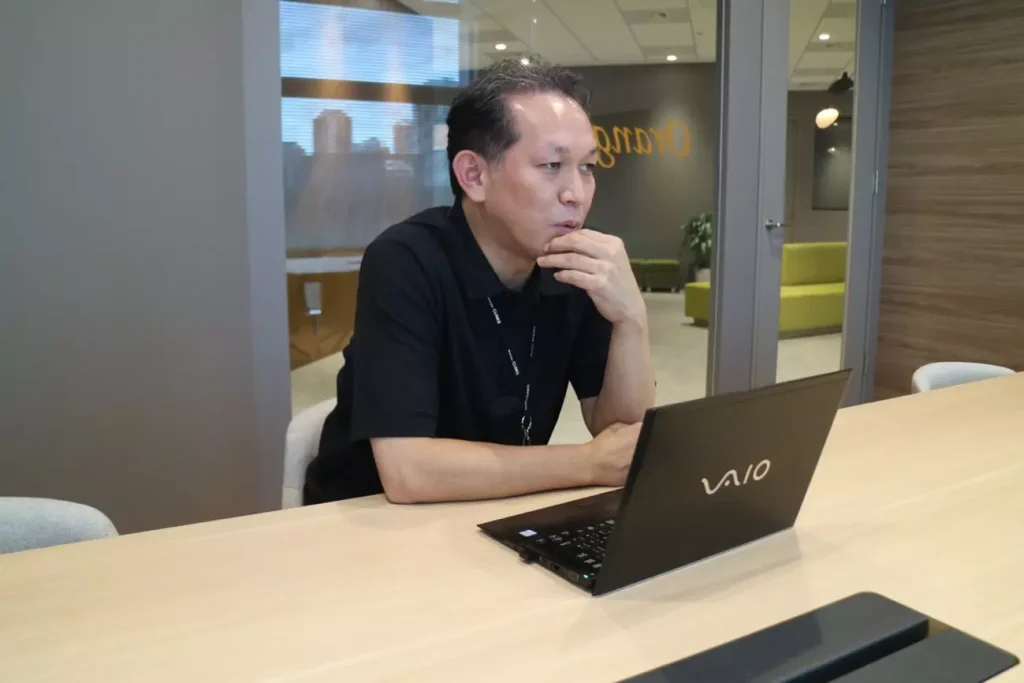
ーー健康経営を実践するなかで大変だったことや、取り組みの効果・反響を感じたのはどのような部分ですか?
小林:やはり社員の平均年齢が若いこともあり、健康問題を自分ごととしてとらえにくいのは大きな課題です。会社が健康経営に取り組んでいることは、社内のポータルサイトやイベント開催時にも発信して周知し、健康意識に関するアンケートを全社員に行なって認識してもらえるよう、試行錯誤しながら取り組んでいます。
効果や反響という点では、在宅勤務制度を推進するなかで、自宅での業務環境を整えるための費用補助をしたのは、従業員から好評価でした。在宅勤務の比率が上がった頃にアンケートを採ったところ、スペースの問題もありましたが、作業に適した机・椅子を用意できていないという意見が多かったのです。そこに対して上限を決めて費用補助したところ、毎月申請が来ている状況です。また、オンラインコミュニケーション手当も反響が大きく、毎月150件くらいは利用があります。
ーー健康経営優良法人認定の評価のフィードバックについて、差し支えなければ教えていただけますか?
小林:弊社は中小規模法人部門と大規模法人部門で2回、健康経営優良法人の申請をしおり、コミュニケーション強化の取り組みについては高い評価をいただきました。一方、健康経営に関する社内の認知度についてはまだまだというところで、どうやって理解を深めていくか、数字を取ってその変化が見られる仕組みを作っているかという部分では、評価が低くなっていました。手探りで進めている状態でしたから、自分たちの不足をたくさん気付かされました。
最初に中小規模法人部門で申請した際はブライト500にも選ばれましたが、昨年挑戦した大規模法人部門は申請内容から違い、ホワイト500にはなれませんでした。いきなり取れるとも思っていなかったので、これは想定内のことですが、まだまだ自分たちのできていない部分に気付けて、勉強になったと思っています。
ーー今後の展望として注力したい取り組みや計画がありましたら教えてください。
小林:今後の目標としては、健康経営優良法人の大規模法人部門でホワイト500を目指しており、中期的な目標を立てて進めているところです。まだ健康経営に取り組みだしてから4年目ですので、社内での認知を高めていく段階にあり、目標到達には、社内で一体感を持って取り組む必要性があると考えます。
例えば生活習慣病予防でいうと、健康診断結果から示されたリスクが高いとされる部分をどのようにして下げていくか施策を提示し、それを何人が利用して改善に向かっているかといった結果を、可視化できる仕組みがほしいですね。それには、全事業部が連携し、会社として一つの目標に進んでいく体制が必要です。
また、オンラインでのイベントやスポーツ補助で、社員間のコミュニケーションもサポートしていますが、さらに強化する施策を打っていきたいと考えています。先ほどご紹介した「ZaiTark」もそうですし、こうしたツールを利用して、物理的な隔たりを感じずに仕事ができる環境を整えてストレスを取り除けるようにしていきたいです。
健康経営は自社のブランディングにもなる取り組み
ーー最後に、健康に関心のある読者の方や、健康経営に取り組まれる企業のご担当者さまへのメッセージをお願いします。
小林:健康経営の取り組みは、営業成績や売上とは違い、今すぐ改善しなければという危機感を持ちづらいものだと思います。そこに対してなるべく早く、経営トップの認識も深めて取り組んでいただくのが重要ではないかと感じています。
弊社は従業員を通年採用していますが、求職者の皆さんは業務内容だけでなく、企業の福利厚生や健康経営、SDGsの取り組みといった部分も判断基準にされるようになっています。従業員の健康維持だけでなく、自社のブランディングという意味でも、今後重要な事柄ですから、企業の皆さまには健康経営に取り組んでいただきたいですね。
ーー本日はお話いただき、ありがとうございました。
今回お話を伺った企業はこちら:CLINKS株式会社
インタビュアー:塩野実莉





