オリンパス株式会社は、内視鏡を中心に医療分野で成長を続けるグローバルカンパニーです。医療分野にかかわる企業として健康経営にも積極的に取り組んでおり、2017年から6年連続で「健康経営優良法⼈ 〜ホワイト500〜」の認定を受けています。
今回は、幅広い健康経営の取り組みを実施しているオリンパス株式会社の人事部門で健康推進を担当している、大橋 宏樹さんにお話しを伺いました。

医療分野を中心としたグローバル企業の「オリンパス株式会社」

ーー本日はよろしくお願いします。まずは御社の沿革やおもな事業内容について教えてください。
大橋さん(以下、大橋):弊社は1919年に、顕微鏡事業で創業いたしました。その後、カメラ製品の開発・製造・販売を行ない、そして戦後まもなく、ある医師からの相談を受け胃カメラの開発に着手し、1950年に世界初となる実用的なガストロカメラを開発しました。以来、医療従事者の方々と二人三脚で内視鏡技術の改良を進め、さまざまな製品・サービスで医療に貢献し続けています。
操業100年を越え、2022年現在では全世界約40の国と地域、30,000人以上の従業員が活躍するグローバル企業となりました。
ーー健康経営を始めたきっかけを教えてください。
大橋:オリンパスとして、健康管理の取り組みを積極的に開始したのは、2008年になります。人事部門の中に、安全衛生・健康推進を担う専任部署を設置し、国内の全グループ会社を統括・管理する体制構築を進めてまいりました。
その後、弊社では真のグローバル・メディカル・テクノロジーカンパニーを目指し、2018年に経営理念の改定、2019年に企業変革プラン「Transform Olympus」を内外に発表し、会社としてグローバル規模での取り組みが進みました。
平行して働き方改革も進めていくなかで、全社規模でのさまざまな取り組みが動いていました。こういった活動を精力的に進めるうえで、その中心となる従業員が高いパフォーマンスを発揮できるよう、健康で安心して働ける環境作りは、会社としても大きな命題となりました。
そこで健康経営を基盤として、企業活動を支えていくことが我々の役割ととらえ、健康経営の取り組みをさらに進化、強化させた経緯があります。
その蓄積として、現在、健康経営を推進する体制が整い、各施策を積極的進めてきていることが、2017年から6年連続でホワイト500の認定につながっていると思っています。
ーーありがとうございます。健康経営の取り組みについて教えてください。
大橋:2018年の4月に「オリンパス健康宣言」を内外に向けて発信しましが、ここが、従来の安全配慮、コンプライアンス確保を主な目的にした健康管理から、健康経営に大きくシフトをしたタイミングであったと思います。
推進体制としては、全国内グループ会社を一元的に管理していること、各拠点に医療専門スタッフを配置していること、健康保険組合とのコラボヘルスが特徴です。特に従業員との接点となる医療専門スタッフは重要な役割を果たしていると考えています。
こうした体制のもと、さまざまな施策を進めてきています。国内グループ会社の全従業員の健康データを一元的に管理する健康管理システムの導入と運用、がん対策の推進、海外駐在員の健康ケア、受動喫煙・禁煙対策などがあげられます。この中でも、特にがん対策は、がん検診から治療と仕事の両立支援まで、力を入れて取り組んでいます。
ーー従業員の健康状態や取り組みについて何か課題に感じていることはありますか。
大橋:ここ数年の取り組みでいうと、それまで長々と活動を続けてきているにもかかわらず、受動喫煙・禁煙対策がなかなか前に進まないといった課題がありました。そこで、「オリンパス健康宣言」を発信した際に、同時に受動喫煙・禁煙対策への取り組みも発表し、トップダウンで、国内グループ全社で足並みをそろえて、一気に受動喫煙・禁煙対策を進めることとしました。
その効果もあって、国内の事業所内では目標を前倒しして全面禁煙が実現し、あとは本来の健康管理の目的に沿って、個人の禁煙対策をいかに進めていくか、というフェーズに入っています。ただ、ここからがなかなか難しく、健康保険組合で導入している無料の禁煙オンライン外来と個人への面接指導などを施策のベースに頑張っているところです。
また今後は、健康管理もさらに予防対策を意識した施策にシフトしていくことが求められています。これは健康経営の主旨でもあり、昨今の働き方の変化への対応という観点でも重要な課題です。こういったニーズ、変化に対応できる体制を整え、継続的な対策、活動を進めていきたいと考えています。
内視鏡によるがん検診を取り入れた定期健診

ーーがん対策に力を入れているとのことですが、具体的な内容を教えてください。
大橋:がん対策では、がんの早期発見・早期治療ということが大切になるので、がん検診を積極的に実施しています。弊社は製品として内視鏡を扱っていることもあり、胃・大腸の内視鏡によるがん検診を定期健診に取り入れ、がん検診の対象年齢となる従業員が希望すれば、費用は健康保険組合の負担で受けることができます。
内視鏡検査以外のがん検診・オプション検査メニューも幅広く用意し、対象年齢の従業員については一部を除き、毎年費用を負担せずに、がん検診を受けられる環境を整えています。
また、2021年度からは、今まで本人止まりだったがん検診結果を取得して、有所見者に対しては精密検査を受けてもらうためのフォローも開始しました。
今後は、有所見者の精密検査受診状況も把握し、精密検査受診率向上に向けて、活動の幅を広げていくことも考えています。
その他、弊社ではがん対策の一環として、治療と仕事の両立支援にも積極的に取り組み就業上の配慮を行なっています。がんの診断を受けた方たちに対しては、健康管理室の産業医、看護職が相談窓口となり個別ケアに当たっています。
一般的に、がんと診断された方は会社を辞めるケースも少なくないようですが、弊社においては、両立支援活動、個別ケア、就業上の配慮などをきめ細かく行なうことで、把握している範囲になりますが、がんを理由で会社を辞めるケースはほぼ発生していません。
ーーありがとうございます。復職支援について、具体的な仕組みをおしえてください。
大橋:復職支援制度といっても、何か特別な仕組みではなく、就業規則として整備されている休暇制度やフレックス制度、私傷病特別休暇などをしっかり活用することが基本となります。
がんの治療は短期間で終わるわけではなく、復職後も定期的な通院が必要となります。そういった治療計画をもとに、社内の休暇・勤務制度をどのように活用していくかを、産業医、看護職が中心となり、時には職場の管理者も交えて、個別の調整を図っています。
こういったきめ細かい対応が、我々の取り組みの特徴です。
ーーがん対策が社内に浸透しているいる理由は何かあるのでしょうか。
大橋:弊社はがん診断・治療を目的とした製品を扱っているので、従業員全般に、病気としてのがんに対する理解が進んでいると思っています。
治療と仕事の両立支援を適切に進めるためには、周囲の関係者の理解と協力が不可欠です。治療・通院を第一に考えた場合、休暇・勤務制度の活用だけではなく、仕事あるいは通勤の負荷も調整する必要があります。こうしたケースにおいても、比較的スムーズに対策を進めることができるのは、社内の風土として、がんという病気に対する理解が浸透しているからだと思っています。
グローバル企業ならではの海外駐在員へのケア

ーーありがとうございます。海外駐在への健康管理について特徴的な印象を受けたのですが、具体的にはどのような支援をしているのでしょうか。
大橋:海外駐在員は、日本国内とは違った環境での生活となりますので、健康管理はとても大切な課題で、会社としてもできる限りのサポートを行なっています。また駐在員本人だけではなく、家族の健康にも気を配ることも大切です。駐在員本人については、赴任前と帰任時の健診が法律で義務づけられているのですが、それに加えて、駐在員の家族の健診も会社として実施しています。
赴任前には、対象の従業員と産業医による個別面談を行ない、健診の結果フォロー、健康管理、感染症関連など必要な情報を伝えています。
また、赴任期間中も年1回の定期健診を義務づけ、現地での健診、あるいは一時帰国時の日本での健診の2パターンで運用しています。現地で健診をする場合は健診結果を日本国内にいる担当の看護職に送ってもらい、産業医が結果を確認し必要に応じてフォローしています。
赴任期間中の相談も適宜受け付けています。担当の看護職を置き、おもにメールになりますが相談窓口を設けています。この窓口からは、赴任後、3カ月、6カ月が経過したタイミングで、対象者全員にメールでコンタクトし、こちらから健康状態を把握するようにしています。
産業医の定期的な現地訪問も実施しています。現地での個別面談、健康セミナー、現地の医療機関の訪問などを通じて、駐在員の健康対策の向上に努めています。ただ、ここ数年はコロナ禍の状況もあって中断していますので、今後再開したいと考えています。
ストレスチェックは、基本的に日本国内の勤務者が法律の対象なのですが、弊社では、海外駐在員も日本国内と同じタイミングでストレスチェックを行ない、必要な従業員に対してはフォローする形をとっています。
ーーありがとうございます。駐在で海外に赴く方も安心して活躍できる環境だと感じました。実際に駐在員の方からの反響があれば教えてください。
大橋:たとえば、赴任後の3カ月と6カ月のタイミングでこちらから送るメールに対しては、ほとんどの方が返信してくれ、「どうもありがとう」といったポジティブな反応が返ってくることも多いです。
そういう意味では、この取り組みが海外に駐在する従業員にとって、安心につながっているのかなと感じています。
会社と健康保険組合が協力して実施する「コラボヘルス」

ーー健康保険組合と協力した健康経営の取り組みも実施しているとのことですが、どのような内容になるのでしょうか。
大橋:健康保険組合が主催する取り組みを、会社も一緒に協力しながら、従業員に積極的に展開するようなコラボ活動を日々実施しています。がん検診もその一つだと思いますが、他に、従業員の健康増進を目的に、ウォーキングをはじめとしたさまざまなキャンペーンを、年間を通して開催しています。
最近はコロナ禍ということもあり生活が内向きになっている方も多いので、キャンペーンの回数を増やし、良い健康習慣の定着を目指して従業員に自発的に取り組んでもらうのが狙いです。
キャンペーンを達成すると、健康保険組合が導入しているWebサイトの健康ナビ、ウェルスポートナビにポイントが付与、蓄積されます。蓄積されたポイントでいろいろな商品やギフト券に交換できます。
こうした取り組みを、従業員の健康増進の一環として健康保険組合とコラボして一緒に進めている感じですね。
ーーありがとうございます。健康経営に取り組むなかで大変だったことや苦労したこと、印象的なエピソードがあれば教えてください。
大橋:少し遡りますが、国内グループ会社全体をカバーする健康管理システムと、統一的な業務運用の導入をあげたいと思います。新システムの導入にあわせて、それぞれの会社でばらつきのあった業務運用を標準化し、それによって、グループ会社の従業員はどの会社で勤務しても、統一的で質の高い健康支援を受けられるようになりました。新システム・業務運用の検討、導入、安定稼働には数年を要し、なかなか馬力のいるプロジェクトだったと思います。ここで構築した基盤が、オリンパスの健康管理体制の一つの大きな特徴であることは、先にお伝えしたとおりです。
もう一点あげると、産業医、看護職を中心とした推進体制の安定的な確保です。健康経営という取り組みにシフトし、我々に求められる役割が拡大してきていますが、従業員の健康を第一に考えた場合、その活動の核となるのは、もちろん医療専門のスタッフです。
どうしてもスタッフの入れ替わりなどもあり、人材確保で苦労することもあります。必要な人材を確保し、全体バランスに配慮しながら、各拠点に配置し、その体制を安定的に維持するためにも、産業医、看護職が働きやすい環境を整えることも、我々の大切な取り組みの一つです。
産業医や看護職と協力しながら従業員の健康を守っていきたい
ーー健康経営の取り組みとして今後の展望などあれば教えてください。
大橋:まず、健康経営と呼ぶにふさわしい体制を確立していきたいと思っています。具体的には、健康管理の施策、活動の結果を評価し、それが経営のパフォーマンス向上につながるシナリオづくり、いわゆるPDCAをしっかり構築する作業を進めています。これにより、健康経営の取り組みが経営活動に貢献することが明らかになることで、この活動に関わる我々にとっても日々のモチベーションにつながると思っています。
また、弊社の大きな方向性として、“グローバル”というキーワードがあります。今までの健康経営は日本国内が中心でしたが、今後はグローバルにおける活動も意識をして進めていきたいと考えています。
ーー最後に、読者の方へメッセージをお願いします。
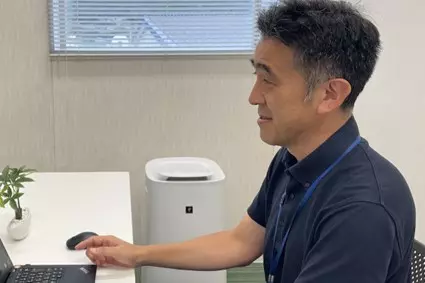
大橋:健康経営の目的は、従業員が健康で、いきいきと働くことができる環境づくりと、個々の従業員が自身の健康管理を主体的に進めるための行動変容を実現することです。
従業員視点での意識をもって、取り組みにあたることがとても重要です。それには、仕組みを整えるだけではなく、従業員との接点を通じて、地道に粘り強く活動を続けることが、最終的にはキーになると思っています。経営あるいは事務方だけでは、目標に到達することはできません。産業医や看護職といった医療スタッフとしっかり協力しながら、一歩一歩前に進めていくことが大切だと思っています。
ーー本日は貴重なお話をお聞かせいただき、ありがとうございました。
今回お話を伺った企業はこちら:オリンパス株式会社
インタビュアー:朝本麻衣子





