
株式会社菊池技研コンサルタントは岩手県大船渡市に本社を置く企業で、公共事業に関わる土木に関する測量や地質調査、土木の設計、補償業務や、情報システム事業として地理情報システムの開発やドローンを使った測量などの事業を展開しています。
2011年に発生した東日本大震災を機に働き方の見直しが必要だと感じ、健康経営への取り組みを開始されました。2019年、2020年には健康経営優良法人中小規模法人部門の認定を取得し、2021年、2022年には健康経営優良法人の上位500社にしか与えられないブライト500の認定を取得されています。
今回は同社の常務取締役であり安全衛生委員会の委員長も務められている佐藤亮さんに、健康経営の取り組みについてお伺いしました。
震災後の激務のなかで、働き方を見直し健康について考える必要があると痛感

ーーまずは御社の事業内容と沿革について教えてください。
佐藤さん(以下、佐藤):弊社は岩手県大船渡市に本社を置く会社で、来年2月に創業60周年を迎えます。おもな事業内容は公共事業のうち、おもに土木に関する測量、地質調査、土木の設計、補償業務を行なっています。また、他にも情報システム事業としてソフトウェア開発やGISと呼ばれる地理情報システムの開発、ドローンを使った測量や空中写真撮影も行なっています。
弊社の特徴的な取り組みとして、菊池技研若手の会があります。若手の会は少子高齢化や人口減少による若手不足、技術継承といった問題に立ち向かうべく、大船渡から一大ムーブメントを起こそうという思いで平成28年に当時の若手有志が立ち上げた組織です。
現在は14名が所属していて、年4回の定例会では勉強会やグループディスカッションの実施に加え、外部講師をお呼びして講演もいただいています。社内に限らず地元の産業まつりへの出展や中学校や高校へ伺い社会人としての経験を話す機会をいただくなど活発に活動していて、各方面から高い評価をいただいています。
ーー健康経営を始めたきっかけを教えてください。
佐藤:2011年に東日本大震災が発生して私たちの住む地域は甚大な被害に見舞われ、弊社も1階が浸水するなど大きな被害を受けました。弊社は公共事業を中心に事業を行なっているため、洪水や津波などの災害時には一日でも早い復旧復興に向けて測量など早急に着手し工事に引き渡す必要があります。東日本大震災の発災後は早期復旧に向けて寝る間も惜しんで業務に励んできましたが、社員も疲労が日に日に蓄積され、終わりの見えない業務に精神的にも追い込まれていきました。
当時は働き方改革が世の中に広まりはじめた時期でもあり、弊社でも仕事の進め方を考え直して社員の健康について考えるいい機会になりました。そして、社員が元気で長く働ける会社を目指し、2016年に社長が全社員に対して健康経営宣言を行ない取り組みが始まりました。
ーー働き方を見直す必要があると感じていても、震災直後はまだまだ忙しい時期でもあり難しい部分もあったのではないでしょうか?
佐藤:健康経営宣言をした2016年当時もまだ震災関係の業務を数多くこなしていて、残業は非常に大きな問題となっていました。その中で働き方改革という、相反することをどのように実現していくかは引き続き考えていくべき課題だと感じています。
ーー非常に忙しい状況だったようですが、社員の健康状態について課題と感じていることはありましたか?
佐藤:業務量が多くなってきて残業や休日出勤もあるなかで、目に見えて疲労の蓄積や集中力が欠けていると感じられることがありました。また、毎年の健康診断において、二次検診の要受診者や特定保健指導受診者もでていました。組織全体の健康に関する分析結果を見ても、生活習慣病へのリスクが高く生活習慣の見直しが必要な状況でした。喫煙者も多く喫煙率は2019年時点で34%となっていて、喫煙率の低下も重要な課題だと考えていました。
社員から好評だった歩行計ホコタッチの活用をメインに、多彩な取り組みで健康を増進

ーー具体的にはどのような施策に取り組んでいますか?
佐藤:創業当初からの取り組みとして、社員全員で毎朝ラジオ体操をしています。現在メインに取り組んでいるのは、ホコタッチという歩行計を社員全員が毎日装着して歩数や歩行生活年齢を競っています。
ホコタッチを活用する大きなきっかけとなったのが、2018年に岩手県で開催された企業対抗チャレンジマッチへの参加でした。チャレンジマッチでは参加企業にホコタッチが貸与され、3カ月間他社と歩数や歩行生活年齢を競いました。社員から好評だったこともあり、チャレンジマッチ終了後の2019年にホコタッチを貸与する株式会社花王様と直接貸与契約を取り交わし、全社員にホコタッチを配付してウォーキングの推奨と健康の意識向上を図っています。また、2019年からは月1回「健康増進ウォーキング」の日を設け、全社員で就業時間内に約30分ウォーキングを行っています。
その他には、2017年から健康ニュース、2019年から健康レシピといった健康に関する情報を、全社員に毎月数回提供しています。2019年からは新たに非喫煙者に対して毎月健康増進手当を支給しています。同年から菊池技研健康経営アワードの開催も始めました。菊池技研健康経営アワードでは、外部講師をお招きしての健康講話や産業医による健康診断結果をもとにした改善事項の指導、ホコタッチの結果から1年間の優良健康増進者およびチームに対する表彰状授与などを行なっています。
2020年からは毎月28日の「いわて減塩・適塩の日」に合わせて減塩弁当の利用促進をしていて、毎月22日の「禁煙の日」は終日禁煙としています。2022年からは岩手県の血圧管理サポート事業に11名が参加して、毎日2回の血圧測定を行ない食生活や運動機会を見直すきっかけづくりをしています。開始時期は定かではありませんが、会議室に卓球台や縄跳び、踏み台昇降機といった運動器具を設置して運動機会も提供しています。
ーーバランス良くさまざまな施策を行なわれていますが、特に健康状態の改善につながっていると感じられている取り組みはありますか?
佐藤:ホコタッチは、今の健康経営の柱と考えています。社員に競争意識を持たせるつもりはないのですが、全社員が毎日ホコタッチを装着して歩行生活年齢を競っています。歩行生活年齢や歩行スピード、装着時間、歩行距離などは毎月全社員に公表しています。
歩行生活年齢以外にもさまざまな結果を公表することで、歩行生活年齢を稼げない人でも装着時間が長ければ上位に名前が出てきます。各自が頑張れるところを拾い上げて社内に見せていけるように工夫していて、単純に歩いた人だけを評価しないところがポイントだと思います。
こまめな情報発信と押し付け感を与えない取り組みで、健康経営に対する意識の浸透を目指す

ーー健康経営を実践するうえで、大変だったことはありますか。
佐藤:健康経営をどのようにして社員に理解してもらうかが大変でした。「やらされている感」や「押し付け感」の少ない取り組みを進めてこられた結果、徐々に社員の理解が深まってきたと感じています。
ーー押し付け感なく健康に対する意識を浸透させるポイントは、どのような点でしょうか?
佐藤:ホコタッチをつけるという、誰でもできるところから取り組みをスタートしました。一生懸命頑張っている人に対して表彰を行なっていますが、歩数が少なくても会社として社員に何かすることは一切ありません。そういった意味では、押し付け感はゼロに近いと思います。
ーー取り組みの重要性を従業員に伝えるために、工夫されたことはありますか?
佐藤:年に1回開催している健康経営アワードで、健康の重要性を伝えています。また、健康診断の結果を踏まえて産業医の先生からいただいたコメントを全社員が集まる機会に説明することもあり、年に1〜2回ほど健康の大切さを話しています。あとは、ホコタッチの順位を毎月全社員に発表しているほか、健康リスクについても月数回全社員に発信するなど、こまめな情報発信をしています。
健康経営は社員の健康維持とともに、企業の価値向上にもつながっている

ーー取り組みをされるなかで、従業員の皆さまからの反響や効果を感じた点はありますか?
佐藤:健康経営アワードの開催やホコタッチの継続的な利用、運動器具の設置などにより、運動に対する意識の向上した社員が増えたと感じます。食生活の面でも減塩弁当を注文する人も増えましたし、社内の自動販売機でトクホ飲料を買うなど食べ物や飲み物にも気を使うようになったと感じています。今年の1月から始めた社内禁煙デーがきっかけとなって1名禁煙に成功しましたし、喫煙率は34%から28%まで減ってきています。取り組みを通じて社員間のコミュニケーションも増えていて、想定外の嬉しい誤算もありました。
また、社内だけでなく社外的にも取り組みが認められて、認定取得や表彰を受賞したことも大きな出来事だと思います。2019年に開催されたいわて健康経営アワードでは、最優秀賞の岩手県知事賞を受賞しました。2019年、2020年には経済産業省推奨の健康経営優良法人中小規模法人部門の認定を取得し、2021年、2022年には健康経営優良法人の中でも上位500社に与えられるブライト500の認定を取得しました。
岩手県内のブライト500の認定企業数は2021年が8社、2022年が4社で2年連続の取得は2社のみです。その中に弊社が含まれていて、大変光栄な認定だと思っています。2021年にはスポーツ庁創設のスポーツエールカンパニーの認定も取得しています。社員の健康を維持できることはうれしいですし、取り組みの結果が社外からも認められたことで企業価値の向上にもつながっていると思います。
心身ともに健康で働ける環境をつくり、会社の発展にもつなげていきたい
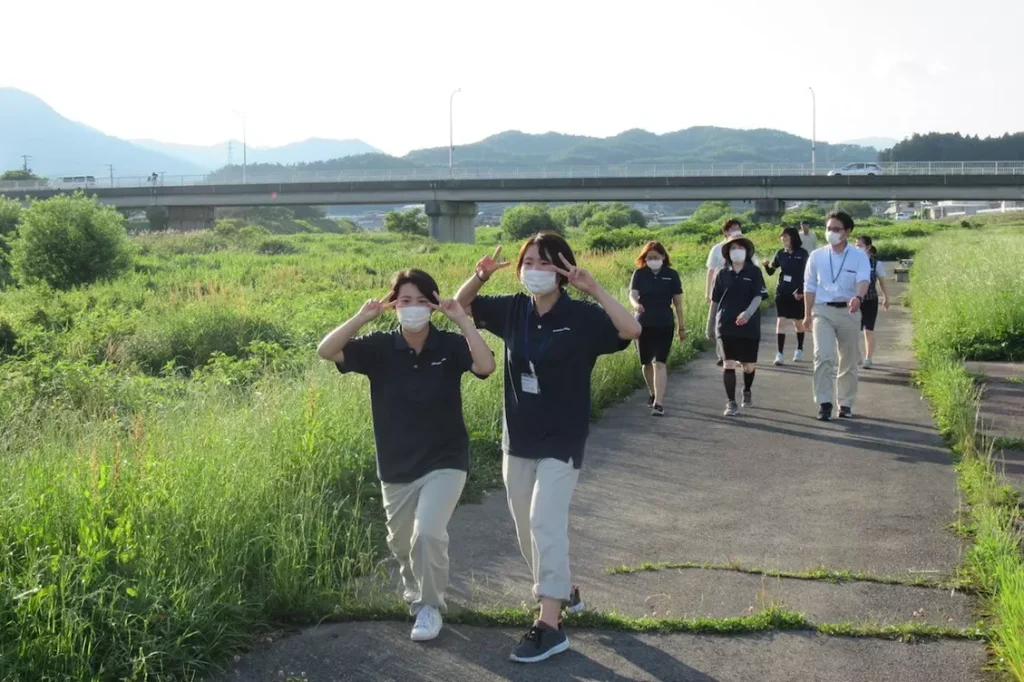
ーー健康経営について、今後の計画や注力されていくことがありましたらお聞かせください。
佐藤:これまでの取り組みは定着してきましたので、今後も社員が無理せず楽しく取り組めるようなことを企画して継続していきたいと思っています。そして、これからは新たにメンタルヘルスの部分にも取り組んでいきたいです。弊社ではメンタルヘルスへの対策があまり進んでおらず、今後重要になると考えています。
健康経営は体の健康だけでなく、心の健康と両立して初めて達成できると思います。そのためにも、メンタル不調の理解や予防を考えていきたいですし、万が一不調になった場合の対策もあらかじめ考えておきたいと思います。その他には、喫煙率を低下させたいと考えています。これまでの取り組みと今後の取り組みに併せて働き方改革も並行し、生産性の向上と業績の向上につなげていきたいと考えています。
ーー健康に関心のある読者や、健康経営に取り組む企業の担当者へのメッセージをお願いします。
佐藤:これから日本は超高齢化社会を迎えるといわれていて、社会的にも大きな問題となっています。特に弊社のような地方の中小企業にとっては、喫緊の課題といえます。高齢化社会にともなう労働人口の減少を少しでも食い止めるためには、健康年齢の引き下げが重要です。年齢を重ねても心も体も元気で自分のことは自分で行なえることが、自分のためにも家族や社会のためにも大事だと思います。
健康経営の実践は、高齢化社会における課題解決に少しでも役立つはずです。多くの人や企業に健康経営を実践していただき、高齢化社会の課題と向き合いながら健康な高齢者を増やしていってほしいと思います。一人ひとりの健康に対する心がけで、個人の心身も企業の業績もひいては日本の財政問題も解決できるかもしれません。ハードな運動である必要はなく、元気な老後を夢見て毎日できることから楽しんで取り組んでみてほしいと思います。
ーー本日は、貴重なお話をありがとうございました。
今回お話を伺った企業はこちら:株式会社菊池技研コンサルタント
インタビュアー:朝本麻衣子
サントリーウエルネスのおすすめ商品はこちら








