
株式会社ワークスアプリケーションズは大手企業を中心に約2,200社(約320企業グループ)の経営やバックオフィスに関わる基幹業務システムを提供しています。企業の生産性向上に貢献する事業を展開するなかで、自社の社員が実力を発揮できる職場環境作りを創業当初から行なってきました。
テレワークやフレックス休暇制度を導入し、2022年からは男性の育児参加を促すため、従来の育児休暇制度の内容を拡充しつつ、男女問わず利用できる制度にリニューアル。また、テレワークによって生じる社員同士や社員と経営層の隔たりをなくせるよう、コミュニケーション機会が増える取り組みも行なっています。
今回は同社 グループ人事統括本部の平山俊大さま、杉山理恵さま、コーポレートコミュニケーションユニットの石川万里子さまに、健康経営優良法人の認定に至った経緯や、社員が働きやすい環境を整える施策についてお伺いしました。
SaaS事業や企業のDX推進で生産性を高める企業

ーーまずは御社の沿革や事業内容について教えてください。
平山俊大さん(以下、平山):ワークスアプリケーションズグループは1996年に設立し、ノーカスタマイズ・無償バージョンアップをコンセプトとした、おもに大手企業に向けたERP(統合基幹業務システム)パッケージソフトウエアを提供している企業です。
近年は会社分割により体制移行し、SaaS事業や中間業者と業務提携して中堅・中小・スタートアップ企業に向けた製品・サービスの提供も行なっています。
SaaS事業の製品としてはテレワーク下での業務を効率化できる、承認・決裁業務を電子化させたワークフローシステムや、国内最大級の登録語彙を搭載したAIチャットボットなど、企業のDXをサポートできる製品を用意しています。
今年4月頃から宣伝広告も出しているのですが、非常に問い合せが増えている状況です。
会社ミッションに基づいた社員が活躍できる環境作り
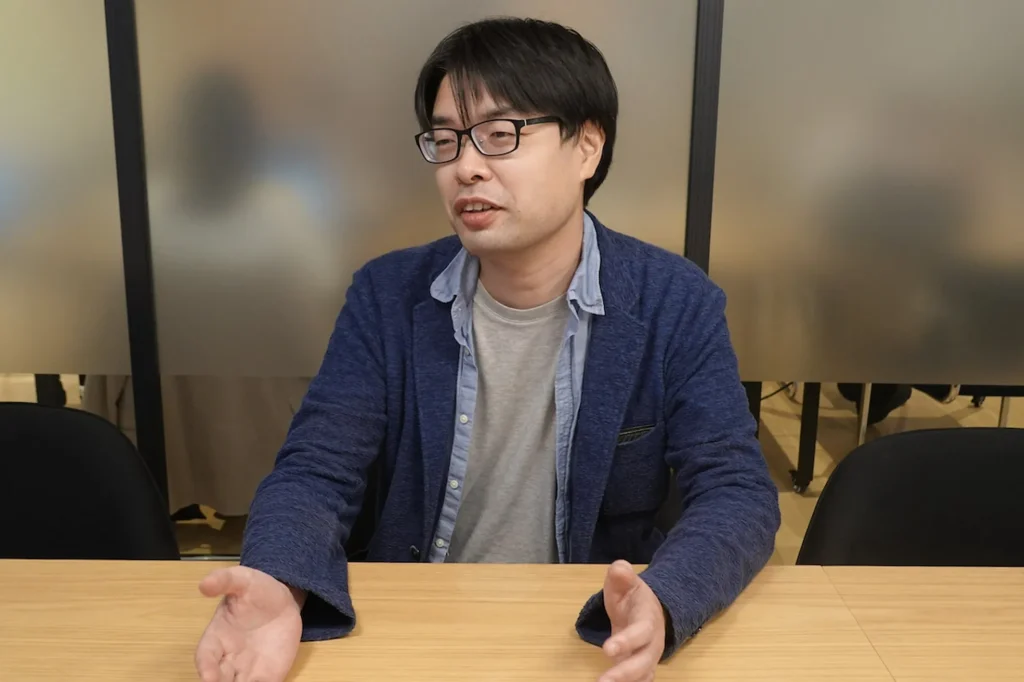
ーー御社が健康経営優良法人の取得を目指したきっかけや、経緯について教えてください。
平山:弊社としては資格やアワードの取得を目指して取り組みを行なったのではなく、会社ミッションに基づいて各種制度・環境を整えていた結果、認定が取れる状態になっていました。
創業当時から企業理念のひとつとして『私たちは「クリティカルワーカー」に、活躍の場を提供します』を掲げています。この「クリティカルワーカー」は、問題解決力が高い、優秀な働きを自然にできる人材といったイメージです。そういった人材に活躍の場を提供するため、社員一人ひとりが実力を発揮できるよう、人事制度や休暇制度を整備してきました。
そのなかで、健康を害しては持てる力を発揮できないことから、社員の健康をフォローする施策も打っており、健康経営優良法人に申請できる状況になっていました。
フレックス休暇に子育て世代を支援する制度も充実
ーーこれまでに取り組まれた健康経営や働きやすい環境を整える施策には、どのようなものがありますか。
平山:弊社はフレックス休暇制度を導入し、国民の祝日をカレンダー通りの固定ではなく、自分の業務都合に合わせて祝日に働いて、別の日に休めるようになっています。この制度を使うと、例えば飛び石連休になっていても、週の途中にある祝日を月曜に移動させて土曜から月曜までの連休を作り、ゆっくり休むことも可能です。
また、性別に関係なく子どもを持つ社員を支援する「WAP FAMO(ファーモ)サポート」も、新制度としてこの9月から導入しました。FAMOとは、英語の“father and mother(父と母)”を略したもので、子どもの病気やケガのときに利用できる特別休暇や、育児休暇中も完全に休むのではなく少しだけ働くことができる半育休制度、育児休暇取得後に復帰した社員への復帰ボーナスといった内容があり、男女問わず利用できる制度にしています。
弊社は平均年齢が34歳ぐらいと介護世代は多くありませんが、いずれ向き合う問題として、介護休暇制度も整えました。以前は介護のために無給で5日間、休暇を取れるようにしていましたが、実際に介護を抱える社員に聞くと日数が足りていないことが判明しました。そこで、まずは日数を増やすことにし、介護休暇として毎年25日間無給休暇が取れるようにしています。
社員の健康に直接関わる取り組みですと、独自の健保組合を立ち上げ、社員の年齢層に適した制度を充実させました。例えば、30歳以降はがん検査を含めた人間ドックを健保の補助で受けられるようになっていますし、インフルエンザの予防接種も無料にしています。
ーーこのほか、社内コミュニケーションの強化もされているそうですが、どのような内容ですか。
杉山理恵さん(以下、杉山):テレワークになって、社内のコミュニケーション機会の減少や、社内のつながりが希薄になったと感じている社員もいるようでした。その対策として、社員同士が顔を合わせる機会や社内報を通じて他部署の状況を知れるよう工夫しています。
社内報は社内で閲覧できるWebで公開し、会社ミッションや、それを経営陣が言葉で解説するビデオ、各部署にフォーカスした記事、新しく入社された方の自己紹介などを掲載しています。そのほか、エンゲージメントサーベイや経営陣からのライブ配信は毎月実施していますし、期初・期中の全体集会で顔を合わせる機会を作ったり、交流機会になるようなイベントを実施したりもしています。
石川万里子さん(以下、石川):新型コロナウイルスの感染状況も落ち着いてきたのを受け、全社参加型の「WAP Forward」というワークショップも最近スタートしました。全社員を対象に、部署をまたいで30名ぐらいずつが対面で集まり、執行役員等の幹部層がファシリテーターとなって、社員同士の対話やワークを通して、各人が自分自身のミッション(仕事を通して成し遂げたいこと)を内省し、会社のミッションとの接点を再認識するイベントです。
平山:ワークショップをやってみての感触としては、結構コミュニケーションに飢えていたのか「隣の人と自己紹介をしてください」となったときに、話がパッと広がる感じでした。普段の業務で関わらない、ワークショップで初めて顔を合わせた人同士でも、積極的に話が弾んだようです。
今回は組織の部長クラスの人も含め、シャッフルされたメンバーで実施しましたが、各自がどのような価値観で行動しているのかを知る機会になったようで、終わったあとに出てきた意見を各現場でシェアしたり、やってみたいと話していたことを実際に実行する機会を提供したりと、広がりを見せています。
女性の活躍を後押しする制度が男女の不平等を生んでいた
ーー御社が施策に取り組まれるなかで、改善が必要と感じた課題はありますか。
平山:課題というと男性社員・女性社員ともに、育児に関する悩みが人事に寄せられていました。今年9月から導入した「WAP FAMOサポート」も、それを踏まえてのことです。
弊社はもともと、女性の活躍推進のための制度として、2004年から「ワークス・ミルククラブ」という制度を導入していました。妊娠判明から出産し、子どもが小学校を卒業するまでの期間、休暇や勤務形態が段階的にサポートされる制度です。
そのなかに、子どもの病気やケガの看護が必要な場合の特別休暇もありましたが、女性だけが対象となっていたのが裏目に出てしまい、男女間での不平等を生んでいました。
例えば社員同士で夫婦だった場合、子どもが熱を出したときのお迎えは有給が取れる母親の役目になってしまい、「パパも手伝ってくれたらいいのに」といった声がありました。また、テレワークになると父親も自宅にいる状態なのに、女性にのみ手厚い支援があるため、女性に育児負担が集中してしまうケースもあったようです。
育児に積極的に関わりたい男性側からも「男性にもワークス・ミルククラブのような制度があれば、もっと育児に関与できるのに……」という相談も寄せられていました。
もともと、男性の育児休暇取得も本人が望めば周りも承諾する雰囲気はできており、これまでに取得している男性社員も多数います。しかし、子どものことで休みやサポートが必要なのは、出産後の期間だけではありません。通常の送り迎えやお世話はもちろん、体調を悪くした子どもの保育園や幼稚園、学校のお迎えや看護など、突発的に発生する事項に使える制度の対象者を拡大させ、内容を強化したのが「WAP FAMOサポート」になります。
石川:男性の育児休暇取得については、他社ではとにかく取得率を上げるために1日だけ休ませるケースもあると聞きます。弊社の場合は本当に必要な人が必要な期間、育児のために休めるよう制度を整えており、自社ながら素晴らしいと思っています。
ーー健康経営の取り組みや働きやすい環境を作っていく施策を実施するなかで、社内の反響はいかがでしたか?
平山: 「WAP FAMOサポート」については、9月に新しくしたばかりですが、9月1日に情報を発信したところ、すぐに社員から3件の問い合せが入りました。自分は対象になるのか、こんなときは利用できるのかといった内容で、社員の関心の高さが伺えます。
すべての意見を取り入れた施策は難しい
ーー労働環境を整備していくなかで、大変だったことはありますか?
平山:あちらを立てればこちらが立たずといいますか、社員全員の声を反映させるのは難しいなと感じています。
現在、テレワークが主体になっていますが、会社に来てコミュニケーションを取る機会がほしい人と、育児を含めた家庭の事情から出社しないで働ける方が良いという人がいます。どちらの意見を尊重するのかバランスを取ったり、希望を公平に叶えたりというのは難しいところです。
「WAP FAMOサポート」の導入に対しても、子供のいる家庭にばかり手厚いのではないかといった意見も、潜在的にあるものと思われます。
我々が掲げる「クリティカルワーカーに活躍の場を」というのは、どのような場を指すのか、「クリティカルワーカー」は誰のことなのかなど、常に立ち返って考える必要があるところです。
直接質問できるライブ配信や部署を超えたワークショップでコミュニケーションを活性化

ーー不公平を生まないために、社内での意見のすり合わせや認識を広める活動も必要かと思いますが、施策内容について社員へのメッセージ発信はどのようにされていますか?
平山:現在、テレワーク下にあるため、経営陣を含めた会社の声を社員に届けづらい状況です。その解決策として、月に1、2回ペースで経営陣からのライブ配信を実施しています。
ライブ配信では、社員から会社や経営陣に聞きたいことをエンゲージメントサーベイ上でコメントとして募り、経営陣が返信する機会を設けています。
コメントには発表された新しい制度について賛同・賞賛する声が寄せられるほか、「この部分はどうなっているのか?」といった問い合せもあり、それに対する補足説明や会社側の思いを返答しています。
社内報として文字で発信し、資料を提示しただけでは伝わりにくい部分を、生の声で話して伝えるという方法です。細かく書かれた資料を読むだけでは伝わりにくい内容も、直接質問に答えてもらえれば主旨が伝わりやすくなります。制度を導入した背景や会社の思いもフォーカスでき、より社員に響いていると感じます。
杉山:ライブ配信は基本的にオフィスから行なっていますので、例えば配信中に社員が飛び入りで参加し、CEOに直接質問を投げかけることもできます。そこから社員とのコミュニケーションに発展することもあり、経営陣との距離が近い状態を作れているのではないかと思います。
会社施策は社員の声を拾い、大きな軸を持って
ーー今後の計画や目標、注力される取り組みがありましたらお聞かせください。
平山:男性の育休取得の取得率は昨年23.8%でしたが、早期に取得率30%を超えたいと思っております。ただ数字を達成できれば良いというのではなく、それぞれの家庭の状況に合わせて最適な働き方を実現できている状況にしたいです。
とはいえ、現在の男性の育児参加のニーズを反映すると、その年にパパになった人のうち、3人に1人くらいが育休を取っている状態は、毎年安定的にあってもいい数字かなと考えています。「WAP FAMOサポート」により、以前なら取得をためらっていた人も前向きに取得するようになればと思います。
なにより、弊社人事の施策内容は、会社ミッションに紐付いた部分が強いので、どうすれば各社員に活躍の場を提供できるのかを、常に検討する必要があると考えています。
ーー最後に、健康経営に取り組まれる企業の担当者や、健康に関心のある読者へメッセージをお願いします。
平山:他社では、テレワークを導入すると社員がサボるのではないか?という不安があるため、導入ができないという話も聞きます。しかし、弊社の実情としては、テレワークだと逆に働き過ぎになる傾向が見受けられました。
これまでは時間が来たら帰宅して、次に働くのは翌日出社してからという勤務形態でしたが、テレワークだと子どもの送り迎えが済んでからとか、寝かしつけが終わってから再開するという形で仕事ができてしまいます。そのため、仕事とプライベートの線引きが難しくなり、知らず知らずのうちに働き過ぎになるのは非常に問題です。
朝起きて仕事をして、終わったら寝るというような生活にもなりやすく、そのなかで、職場内での雑談などのちょっとしたコミュニケーションの機会も少なくなってくるので、集中して仕事ができる半面、ふとした時に働く意義を見失うこともあったりするようです。
心身の健康と仕事のパフォーマンスを考えると、こうした状況は健全ではありません。ですから、テレワーク下では社員のサボりを注視するのではなく、社員の健康や心身の状態を見ていくのが大事だと考えています。
コロナ禍になって2年半経過し、弊社も手探りで対策を取っている状況ですが、社員の声に一生懸命耳を傾けています。テレワークによって、声を拾いづらい状況ですが、よりアンテナを高くして社員の声を聞き、会社の制度に反映させる取り組みを継続させていきます。

杉山:会社として何かに取り組む際は、ぶれない一つの軸を持っていることが重要だと思います。弊社は「クリティカルワーカーに活躍の場を」という会社ミッションがあり、これを軸として制度や取り組みを考えてきました。
単純に「社員の満足度を上げる」「女性を活躍させる」「育休の取得率を上げる」などという、目先の問題だけを考え、達成する数字を追うだけでは、取り組みの本質を見失ってしまうと思います。大きな軸を持って施策を進めれば内容に一貫性がうまれますし、本質的な課題に対して改善を図る施策が実行できます。
ーー本日はお話いただき、ありがとうございました。
今回お話を伺った企業はこちら:株式会社ワークスアプリケーションズ
インタビュアー:朝本麻衣子
サントリーウエルネスのおすすめ商品はこちら








