
愛知県名古屋市に本社を構える株式会社名豊は、医療や介護、福祉などの社会保障制度に関するコンサルタント事業を展開する会社です。多くの企業にウェルビーイング経営を提案し、健康経営認証取得を支援してきた同社。
顧客の健康経営をサポートするうえで、まずは自社が率先して取り組む必要があると考え、健康に関する活動を積極的に推進してきました。2017年から健康経営優良法人(中小規模法人部門)を取得し、2021年には上位500社のみ認められるブライト500を取得しています。
今回は、株式会社名豊の代表取締役会長 中野宏昭さんと代表取締役 小池武史さんに健康経営の取り組みについてお話を伺いました。
「人にやさしいまちづくり」を掲げ、建設コンサルタント事業から社会福祉・医療分野の支援事業へ発展

ーー本日はよろしくお願いいたします。早速ですが、御社の沿革やおもな事業内容について教えてください。
小池さん(以下、小池):当社は、名古屋に本社を構え、1982年にまちづくりの建設コンサルタントとして創業しました。具体的には、公園・道路・住宅団地などの計画・設計業務を官公庁から受託し、地域のまちづくりを支援する事業です。
そしてバブル崩壊後、まちづくりの考え方が「コンクリートから人へ」と変化を遂げるなかで、弊社の業務も「人にやさしいまちづくり」を掲げ、障がい者、子ども、高齢者に優しいまちづくり、さらに少子高齢化が進むなかでの高齢・地域福祉、子ども子育て、男女共同参画、健康・食育など社会保障関連分野の調査、計画策定業務を中心に中部・関西から全国へと地域貢献をして参りました。
2008年に制度改正により特定保健指導がスタートすると同時に、地元愛知県内の市町村と関西地域の和泉市、大東市、岸和田市などの市町村の特定保健指導やヘルスアップ事業、重症化予防事業にも貢献しております。
2017年には、経済産業省が推進する「健康経営」にともなう、健康経営優良法人を取得し、大手・中小の民間企業への「健康経営優良法人」の認証支援コンサルタントとして東京や、地元大手上場企業、中小企業への認証取得支援を展開しています。
最近では、医師、研究所とのアライアンスによる従業員への「メンタルヘルスケア」「女性特有の疾病対策」に特化した健康経営活動に加えて、「働き方改革」「SDGs」「ウェルビーイング」などの分野の効果を狙った健康経営活動サポート、ソリューション提供が注力している分野です。
ーーありがとうございます。事業としても健康経営に深い関わりがあるのですね。
小池:創業者である中野の両親が病院医療関係者で、中野自身、幼少期から病気や医療に関する話題に触れることが多く、特に予防についてよく注意されて育ったそうです。もともと健康意識の高い環境だったのだと思います。
そうしたなか、建設コンサルタントから社会保障分野へ業種転換後、「健康日本21」の計画づくりを官公庁から受託しました。その業務に携わるなかで「一人の健康は一人では実現できない、自助・共助・公助が大切」というヘルスプロモーションの考え方、さらに「人の一生は一般に加齢とともに健康からフレイル、疾病・要介護状態、死へ」の過程を歩むとされていることを学びました。
そこでいかに健康寿命を延ばすかが重要と考え、まずは少しでも早く若いときから「0次予防」に努めることの重要性を伝えるため、民間企業の健康経営活動と健康経営優良法人認証のお手伝いをすることとなりました。
現在は、東京・名古屋を中心に全国展開しており、従業員の健康=企業の発展をコンセプトに健康経営活動を行なっております。
生活習慣の見直しを軸に、健康意識向上のための施策を実施

ーー御社の健康経営の取り組みについても教えてください。従業員の皆さんの健康状態について、改善が必要だと思われたことはありましたか?
小池:弊社の従業員の傾向として、性別・年代関係なく脂質リスクの保有率が約6割と高い状態でした。特に、血圧の高い8人中6人が脂質異常リスクを抱え、さらにそのうちの2人は糖代謝リスク、5人は肝機能障害リスクを抱えており、今後、生活習慣を改善しなければ健康状態が悪化する懸念がありました。
生活習慣リスクを高める要因は、日中活動量が少ないことや、食生活の問題が多くを占めていると考えています。
社内アンケートでは、「人と比べて食べる速度が速い」「就寝前の2時間以内の夕食」「朝食を抜くことが週3回ある」などの回答が挙げられたほか、残業による睡眠不足やストレスなども脂質異常をきたす要因となっている回答が多く見受けられました。
また、日常業務に影響するプレゼンティズムの状況としては、腰痛や花粉症、睡眠不足者がいること、アブセンティズムにおいては、メンタル不調者、生活習慣病や腰痛などによる欠勤も課題でした。
今後の取り組みにおいては、働き方改革と合わせて生活習慣を改善するとともに、メンタルヘルスケアに取り組んでいく必要性を感じています。
ーー健康課題に対する施策について詳しく教えてください。
小池:具体的な施策としては、独身者の食生活や運動、休養などの生活習慣の改善のために個人別のヘルスプランを立て、毎月1回、管理栄養士による予防のための保健指導を実施しています。
その他、生活習慣の改善を軸にフィジカル・メンタルの両面を網羅するような細やかな取り組みを行なっています。例えば、睡眠不足者に対する月1回の定期的なメンタルチェックやコーピングリストの活用によるセルフケア、ラインケアによる予防と指導です。
コーピングリストというのは、自分自身でストレス解消になるもの、例えば好きな音楽を聴いたり、好きな映画を観たりといった、ストレス解消法をリストにしておいて、ストレスを溜めないようにセルフケアしてもらう取り組みです。提携しているメンタルヘルスケアの先生から指導いただいています。
また、年に一度、管理栄養士や産業医の指導のもと、健康診断結果と生活アンケート調査に基づく「マイヘルスプラン」を作成しています。このプランを各課で共有し、朝礼時などに従業員同士で声をかけ合うことで日々の健康意識の向上や習慣化に取り組んでいます。
女性特有の疾患に対するセミナーの実施や、感染症予防のワクチン接種費用補助など基本的なところも網羅していると思いますね。
ーー健康経営を実践するうえで、苦労されたことや工夫されたことはありますか?
中野さん(以下、中野):弊社の健康課題として、やはり若い人ほど健康を意識しづらい点があります。さらに健康に対する意識は、家庭環境などいろいろな要素が影響するため個人で捉え方が大きく異なります。
いかに早い時期から健康意識を高めるか、予防に努めていくかが大事ですが、それは会社からの働きかけも必要だと考えています。当社では、そういった意識付けの取り組みの一環として「健康経営アドバイザー」の資格取得の奨励や、資格取得に対するポイント制度を導入しています。健康に関心を持つきっかけとして、社内制度が役に立っているわけです。
健康に対する危機感だけではなく、健康であることの喜び、大切さを感じてもらい、それをどう仕事に結びつけていくのかを考えていきたいですね。一方で、活動を強制したり、抑圧したりすると逆効果になる場合もあると思います。個々に合ったアプローチになるよう工夫しています。
小池:大変だと感じる点ですと、個人の生活に関するところまで、会社が言及しづらいこともあります。社内でも食事や運動に関するセミナーなど、専門職の方が指導をしているものの、実際にどのくらい浸透しているのか、従業員が実行してくれているのかは、非常に見えづらく、状況を把握し難いです。
特に若い方を中心に、「自分は大丈夫」「自分は元気だから関係ない」という感覚があるように感じます。健康に対してのモチベーションを上げるのが難しいですね。
工夫した点については、会社のイベントや行事を健康経営の一環として取り組んでいるところです。
ーー会社の行事やイベントをどのように健康経営に紐付けているのでしょうか。
小池:運動不足解消の取り組みについても、地域貢献と組み合わせたボランティア活動の一環としています。以前からお付き合いのある神社の清掃ボランティアを定期的に行なっているのですが、神社の最寄り駅から5キロほどの距離をウォーキングしながら向かい、清掃活動をし、その後、地域の方と食事会をするというような活動です。
中野:地域の健康福祉支援に携わってきた当社ならではの強みでもあるのですが、地域への貢献をとても大切にしています。地元企業のイベントの一角に無償でブースを設置し、来場者の方の健康チェックや体力測定、栄養相談を実施したり、親子で参加できるヨガ教室を企画したり、地域の方の健康支援にも積極的に参加しています。
今後は「健康経営のマンネリ化」の解消支援へ
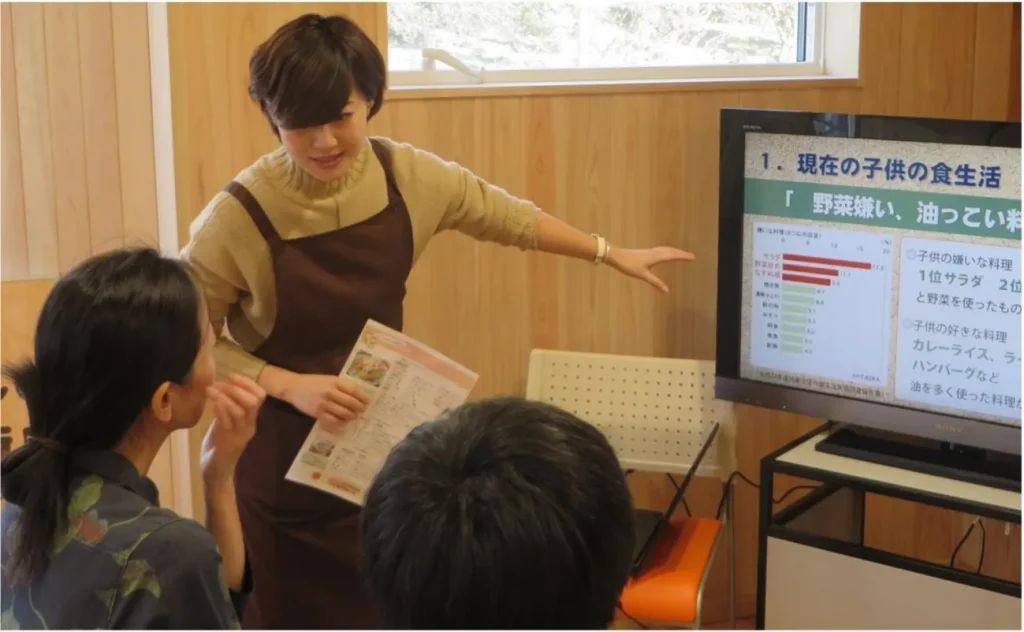
ーー取り組みによる社内外の反響はいかがですか?
小池:社外からの問い合わせが増えましたね。当社の認証取得の影響もあると思いますが、健康経営の認知度が高くなってきたことも実感しています。Webサイトの問い合わせフォームからご相談をいただくことも増えました。全国各地の企業様からお声がけをいただいています。
問い合わせの内容も、すでに認証を取得した企業様から「健康経営のマンネリ化」についてご相談いただくケースが増えています。認証制度がはじまって5年が経ちますが、健康経営の活動をどのように継続すれば良いのか、新しい取り組みに何をすれば良いのか、といった内容で継続支援の引き合いが増えてきたことも昨今の変化です。
ーー今後の展望について教えてください。
小池: 現在ご相談が多いメンタルヘルケアのサポートや健康経営活動のマンネリ化の解消、健康経営活動を展開すればするほど事務局が疲弊してしまうなど、健康経営に関する課題は企業によってさまざまです。
企画運営から実施までの業務代行など、これまでの健康経営優良法人の認証取得の支援と健康経営活動を中心に展開して参りましたが、今後も継続的な取り組みとするための支援が新たなニーズとしてとらえています。
今後は、専門医とのアライアンスによるセルフケア・ラインケアによるメンタルヘルスケアの総合的な支援や健康経営活動のエージェント契約による支援のパッケージ化を進めてまいります。
また、健康経営を導入したのち、企業に対してどのような効果が得られたのか、経済産業省が策定している「健康投資管理会計ガイドライン」による効果測定など、健康経営が従業員の健康増進や生産性の向上、リクルート効果へとつながっているのかといった健康経営活動の「効果の見える化」を推進していきます。
ーー最後に読者へのメッセージをお願いします。
中野:健康は投資ととらえていかなければならないと感じています。まだまだ、中小企業のなかでは「健康は個人が務めること」という考えが根強く、従業員の健康維持にお金をかけることが浸透していません。
しかし、新型コロナウイルスの流行をきっかけに、多くの企業が従業員の健康状態が業績に影響することを実感したと思います。費用対効果という意味でも、従業員の健康問題には会社からの働きかけが必要です。
小池:ウェルビーイングとは、「健康」「環境」「人間関係」「やりがい」「経済」5つの分野がバランスよく満たされることで得られるものです。健康経営はウェルビーイングに向けた一丁目一番地であることは間違いありませんが、健康経営優良法人を認証取得することが目的ではなく、ウェルビーイングを目指すための手段であるととらえています。また、健康経営活動がウェルビーイングの各要素に横串を通すことで、一体的かつ体系的に推進していくことが可能です。
弊社のコアコンピタンスである健康分野の専門家として、これまで培ったノウハウを最大限に発揮することは勿論のこと、あらゆる分野の企業様とのアライアンスにより、民間企業の健康経営活動を支援することでウェルビーイングの実現をご支援いたします。
ーー本日はお話をお聞かせいただき、ありがとうございました。
今回お話を伺った企業はこちら:株式会社名豊
インタビュアー:朝本麻衣子





