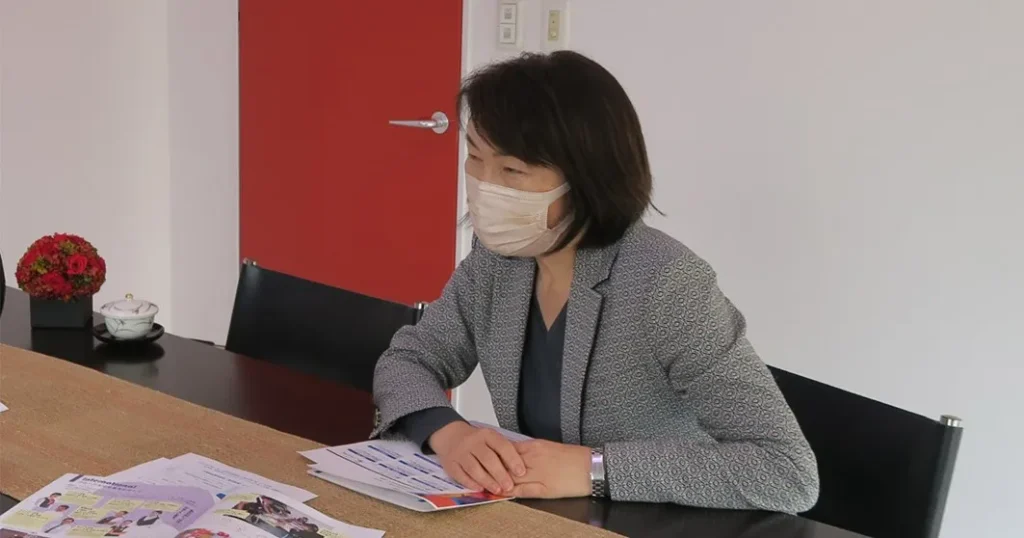
株式会社くまもとKDSグループは、熊本市を拠点に自動車教習所やドローンスクール、福祉事業など幅広い事業を展開している企業グループです。
同社は、グループ全体での健康に対する取り組みが高く評価され、2017年に厚生労働省の「健康寿命をのばそうアワード2017」の健康局長優良賞を受賞しました。また、経済産業省の「健康経営優良法人」に制度創設以来、7年連続で認定されています。社員の健康増進がより良い職場環境の実現につながり、さらに地域を巻き込んだ健康経営にも注力しているのだそうです。
今回は、株式会社くまもとKDSグループ代表取締役 永田佳子さんにお話を伺いました。
社員の病気をきっかけに、健康の大切さを実感

ーー本日はよろしくお願いします。まずは御社の事業内容について教えてください。
永田さん(以下、永田):当社は、熊本県内に自動車教習所を2校、ドローンスクール、技能講習トレーニングセンター、福祉事業など5つの事業を展開している企業グループです。
自動車教習所の「菊池自動車学校」「熊本ドライビングスクール」では、初心運転者の運転者事故率0%を目指し、また地域の交通安全教育センターとして教習を行なっており、初心者から上級者まで幅広いレベルの方々に対応したカリキュラムが充実しております。
技能講習トレーニングセンターでは、熊本労働局長登録の教習機関としてフォークリフト・クレーンなどの専門技能トレーニングを実施しております。
その他、発達障害やグレーゾーンの方のための障害福祉サービス事業も行なっており、職業体験や自己理解を深めるプログラムを通して就労支援事業も展開しております。
ーー健康経営を始められたのには、どのような背景があったのでしょうか。
永田:私が代表取締役に就任した頃、立て続けに2人の社員が病気で亡くなったことがありました。生活習慣病が原因の病気だったため、あらためて社員の健康について考えるきっかけとなった出来事です。
社員を立て続けに亡くしたことは会社にとっても大きな悲しみでしたが、ご家族への影響もとても大きいものだったと思います。
生活習慣病は、痛みなど自覚症状がないケースも多く「気付いたときにはすでに手遅れ」になっていることもあります。当時、社内全体で健康意識が低かったこともあり、健康経営に取り組む必要性を感じました。
最近では、アブセンティーズム・プレゼンティーズムという言葉もよく聞くようになりましたが、体調が悪い社員に対して会社も成果を求めることはできません。社員の健康は個々の活躍に大きく影響しますし、会社としても元気でハツラツとしている人が多いほうが全体のモチベーションにつながると思います。経営者としては、生産性向上への期待もありました。
「二次検査の受診徹底」と「禁煙施策」を2つの軸に

ーー健康経営に取り組むにあたり、社員の皆さんの健康課題はありましたか?
永田:まず、健康診断の二次検査受診率が低いことが気になっていました。当時、有所見となっても個人の判断に任せたままで受診のフォローができていませんでした。
健康経営に取り組むきっかけになった2人の社員も、生活習慣病が起因となる病気で亡くなっています。どのような小さな指摘でも、まずは検査にいくことを当たり前にしたいと思いました。
そして、基本的な生活習慣そのものにも課題がありましたね。ランチの時間にスタッフルームを覗くと、カップラーメンや唐揚げばかりを食べていて、野菜が少なかったり、自分の好きなものばかりで偏った食事内容だったり。喫煙についても、スタッフルームの壁が変色するほどの状態だったので改善が必要だと感じていました。
ーー健康課題に対する施策の内容についてもお聞かせください。
永田:まずは、社員の健康診断結果をデータ化して健康状態を把握することから始めました。健康診断の結果は、産業医とシェアして受診後に1on1の面談を実施しています。また要再検査の該当者は、必ず検査を受けるよう就業規則でも定めました。
継続的な治療や投薬が必要な方は、定期的な報告書を提出してもらうことで通院が中断しないようフォローもしています。報告書は、自身の健康状態や治療内容を理解する良い仕組みになっていますね。病識がつくことで、自己コントロールもしやすくなると思います。
食生活の改善には、健康的な社食の配食サービスを導入しました。管理栄養士さんが考案したバランスの良い献立を、半額会社負担で社員に提供しています。汁物もついていますし、野菜も豊富で社内でも好評です。
コンビニで社員をみかけた際に、キャベツの千切りの袋を5つくらい持っていたので、声をかけたら「みんなの分の買い出しにきた」と。その社員からベジファーストを意識していると聞いたときには、健康意識が変わってきたことを感じましたね。
熊本県は農業が盛んなため知り合いに農家さんも多いので、コンビニの野菜を買うより農家さんから新鮮なものを届けてもらえるようにして、社内でバイキング形式のサラダを出すようにしました。バイキング形式だったため、コロナ禍の影響でしばらくストップしていますが、徐々に再開していきたいと思っています。
その他、運動習慣やストレス対策なども継続して行なってきました。
ーー特に注力した施策はありますか?
永田:禁煙化については、健康経営を始めた当初から注力して取り組んできました。当社の喫煙率は80%ほどで、男性社員のほとんどが喫煙者でした。禁煙はトップダウンで一方的に吸えないようにするとやはり反発も出てきます。
そこで、「一般社団法人 くまもと禁煙推進フォーラム」に参画し、喫煙の有害性について学ぶことからスタートしました。専門家やドクターによる講演で、自身の体への影響や副流煙による家族への影響も学び、禁煙を決意してくれる社員が増えはじめました。
タバコが体にどのような影響を与えるのか、実演を交えた講演は説得力があったのだと思います。タバコの仕組みを理解し、本人が禁煙を決意したうえで喫煙ができない環境を用意して禁煙を支援してく。これが当社の取り組みの方針でした。

2017年には敷地内全面禁煙にして、2021年にはオンライン外来を活用して喫煙率0%を達成。これは社外からの反響も大きかったですね。
企業を超えてつながる健康経営

ーー健康経営に取り組まれて、効果や変化を感じたことはありますか?
永田:健康意識アンケート調査から、社員の意識が変わったことを感じます。日常生活のなかで健康に気を配るようになったという回答が多いです。禁煙した社員が、自身の成功体験をご家族に広めてくれた話も耳にしました。
自動車学校の教習生の生徒さんにも広めている社員もおり、私は彼らのことを「禁煙インフルエンサー」と呼んでいます。
ーー健康経営優良法人の認定を取得されて、対外的なメリットはありましたか?
永田:健康経営を通してステークホルダーが広がったのは大きなメリットでした。健康経営優良法人の認定は、対外的にもわかりやすさがあるため社外からお声がけいただく機会も増えます。事業領域や利害に関わらず、社会が良くなる取り組みで協働できるのは良い経験です。
また、当社は外国籍のスタッフも数名在籍しています。このスタッフたちの就労ビザを取るのに健康経営優良法人の認定が役立ちました。認定を取得している企業の場合、カテゴリー1という東証一部上場企業並みに手続きが簡単になります。
今後、多様な労働力が必要となる日本では、多くの企業で取得するメリットになると思いますね。
「熊本県を日本一健康する」ことを目指して

ーー健康経営について、今後予定されている施策などはありますか?
永田:社内ではだいぶ健康意識が根付いてきたので、今後は社員の扶養者、奥様だったりお子さんだったりの健康も支援できたらと考えています。
やはり、ご家族が体調を崩されると社員も心配でしょうし。扶養として当社の社会保険に加入されているご家族の方には健康診断を受診いただくよう手紙を書いています。受診率が100%近くになった年もありましたが、だんだん受診される方が減ってきています。
お子さんのことを優先すると、なかなか奥様自身の時間を取れないのもわかりますが、女性特有の疾患リスクもあるので必ず受診いただきたいですね。
もう一つは「熊本県を日本一健康にしよう」という目標を掲げて、2020年くまもと健康企業会が発足しました。昨年9月のセミナーには80社を超える企業に参加いただきました。
実は、協会けんぽの場合の社会保険料は県によって金額が異なります。この仕組みを知ったときに、自社だけで取り組むのではなく熊本県全体で進めていく必要性を感じました。
前年度に使われた医療費によって当年の保険料率が変動します。経営者にとっては、健康な従業員が増えて医療費が下がれば保険料率も下がってくるので、このあたりの仕組みも理解したうえで健康経営に取り組んでほしいですね。
地道な活動ではありますが、長い目でみれば、熊本県全体の医療費が減って保険料率も下がるので企業のメリットになると思います。
ーー最後に、健康に関心のある読者の皆さんへメッセージをお願いします。
永田:健康は一日にしてならず、と言いますが本当に毎日の積み重ねです。職場でお互いが励ましあってできることから取り組んでほしいですね。そういった活動の輪が、企業を超えて広がれば、日本全体の医療費を抑えられるのではと思います。
将来を背負う若い方々に負担をかけないよう、今私たちができることをしなければと感じます。そういった意識を一人でも多くの経営者の方が持ってくださると良いですね。
ーー本日はお話いただき、ありがとうございました。
今回お話を伺った企業はこちら:株式会社くまもとKDSグループ
インタビュアー:朝本麻衣子
サントリーウエルネスのおすすめ商品はこちら








